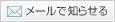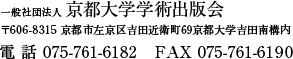ホーム > 書籍詳細ページ

唐代初期に活躍して南山律の開祖として名高い道宣は、また中国最大の仏教史家でもあった。しかし、伝わる事蹟には疑わしいものが多い。本書は、既存資料を徹底的に精査し、彼の波瀾に富んだ生涯と旺盛な著作活動の全容を初めて中国仏教史の中に位置づけた。京都で発見された著作『続高僧伝』中の玄奘伝の翻刻は特に資料性が高い。
藤善眞澄(ふじよし ますみ)
関西大学文学部教授
1934年 鹿児島市生まれ。
1964年 京都大学大学院博士課程単位取得退学。
1968年 神戸女子大学助教授。
1971年 関西大学助教授。
1975年より現職。
主な著書
『諸蕃志』(関西大学出版部、1990年)
『アジアの歴史と文化(2)』(編者、同朋舎出版、1994年)
『安禄山』(中公文庫、2000年)ほか。
関西大学文学部教授
1934年 鹿児島市生まれ。
1964年 京都大学大学院博士課程単位取得退学。
1968年 神戸女子大学助教授。
1971年 関西大学助教授。
1975年より現職。
主な著書
『諸蕃志』(関西大学出版部、1990年)
『アジアの歴史と文化(2)』(編者、同朋舎出版、1994年)
『安禄山』(中公文庫、2000年)ほか。
序
第一章 僧祐より道宣へ
はじめに
一 『出三蔵記集』と『大唐内典録』
二 『弘明集』と『広弘明集』
三 護法ー道教と排仏論
四 三時観——末法思想——
むすび
第二章 道宣の出自——呉興の銭氏——
はじめに
一 行状記と郷貫
二 呉興長城の銭氏
三 陳朝の成立と銭氏
四 道宣の祖と父、母
五 陳の滅亡と銭氏
第三章 道宣の前半生
はじめに
一 生卒年と入道
二 和上慧〓
三 受戒前後
四 阿闍梨智首
五 日厳寺、そして崇義寺へ
第四章 中年期の道宣——遊方と二・三の著作——
はじめに
一 遊方へ
二 沁部より魏土へ
三 『四分律行事鈔』の成立
四 『〓補随機羯磨』と『拾毘尼義鈔』
五 江南・湖北巡歴と『浄心誡観法』
第五章 晩年の道宣
一 長安帰着
二 豊徳寺入山
三 玄奘の訳場列位
四 西明寺上座
五 道宣と玄奘
六 道宣と道世
第六章 『続高僧伝』玄奘伝の成立——巻四・玄奘伝——
一 新発見の興聖寺本
二 興聖寺本の構成
三 玄奘伝の校合
四 玄奘伝の校合
五 興聖寺本の成立年次
むすび
續高僧傳〓第四
第七章 『続高僧伝』管見——興聖寺本を中心に——
はじめに
一 増広補筆をめぐって
二 王朝の系譜——正統論——
三 排列と構成
第八章 道宣の入蜀と『後集続高僧伝』
はじめに
一 蜀地行脚
二 『後集続高僧伝』
三 入蜀と『後集続高僧伝』
四 入蜀の意義
第九章 衞元嵩伝成立考
はじめに
一 『続高僧伝』と衞元嵩伝
二 杜祈説話の意味するもの
三 衞元嵩伝と小説
四 『後集続高僧伝』と衞元嵩伝
五 入蜀と衞元嵩伝
むすび
第十章 道宣と礼敬問題
一 礼敬と『釈門帰敬儀』
二 沙門不応拝俗表と道宣
三 拝不拝朝議の行方
四 不応拝俗論をめぐる彦〓と道宣
第十一章 道宣の絶筆三種
一 入寂
二 『律相感通伝』
三 『関中創立戒壇図経』
四 浄業寺戒壇
五 『中天竺舍衛国祇〓寺図経』
六 絶筆余譚
第十二章 薬師寺東塔の〓銘と西明寺鍾銘
一 薬師寺東塔
二 東塔〓銘
三 西明寺鍾銘
四 鍾銘と『広弘明集』
五 鍾銘より〓銘へ
六 鍾銘請来
附 篇
附篇第一章 北斉系官僚の一動向
一 隋文帝の誕生説話
二 『開皇起居注』
三 王劭とその周辺
四 周隋革命
五 著作郎王劭の革命説
六 隋朝と仏教
附篇第二章 王劭の著述小考
一 王劭略伝
二 『斉書』述仏志
三 述仏志と釈老志
四 『隋書』と王劭
五 『舎利感応記』
附篇第三章 末法家としての那連提黎耶舍——周隋革命と徳護長者経——
はじめに
一 那連提黎耶舍伝
二 耶舍の訳経事業
三 『大集月蔵経』と『蓮華面経』
四 『徳護長者経』
むすび
附篇第四章 中国の典籍に表われた祇〓精舍
はじめに
一 『金剛経』六訳と祇〓精舍
二 安世高の舍衛国・祇樹給孤独園
三 支婁迦讖・安玄・竺法護の祇〓精舍
四 法顕と祇〓精舍物語
五 中国の祇〓精舍縁起
六 『大唐西域記』と『中天竺舍衛国祇〓寺図経』
初出書誌一覧
索 引
要旨(中文、英文)
第一章 僧祐より道宣へ
はじめに
一 『出三蔵記集』と『大唐内典録』
二 『弘明集』と『広弘明集』
三 護法ー道教と排仏論
四 三時観——末法思想——
むすび
第二章 道宣の出自——呉興の銭氏——
はじめに
一 行状記と郷貫
二 呉興長城の銭氏
三 陳朝の成立と銭氏
四 道宣の祖と父、母
五 陳の滅亡と銭氏
第三章 道宣の前半生
はじめに
一 生卒年と入道
二 和上慧〓
三 受戒前後
四 阿闍梨智首
五 日厳寺、そして崇義寺へ
第四章 中年期の道宣——遊方と二・三の著作——
はじめに
一 遊方へ
二 沁部より魏土へ
三 『四分律行事鈔』の成立
四 『〓補随機羯磨』と『拾毘尼義鈔』
五 江南・湖北巡歴と『浄心誡観法』
第五章 晩年の道宣
一 長安帰着
二 豊徳寺入山
三 玄奘の訳場列位
四 西明寺上座
五 道宣と玄奘
六 道宣と道世
第六章 『続高僧伝』玄奘伝の成立——巻四・玄奘伝——
一 新発見の興聖寺本
二 興聖寺本の構成
三 玄奘伝の校合
四 玄奘伝の校合
五 興聖寺本の成立年次
むすび
續高僧傳〓第四
第七章 『続高僧伝』管見——興聖寺本を中心に——
はじめに
一 増広補筆をめぐって
二 王朝の系譜——正統論——
三 排列と構成
第八章 道宣の入蜀と『後集続高僧伝』
はじめに
一 蜀地行脚
二 『後集続高僧伝』
三 入蜀と『後集続高僧伝』
四 入蜀の意義
第九章 衞元嵩伝成立考
はじめに
一 『続高僧伝』と衞元嵩伝
二 杜祈説話の意味するもの
三 衞元嵩伝と小説
四 『後集続高僧伝』と衞元嵩伝
五 入蜀と衞元嵩伝
むすび
第十章 道宣と礼敬問題
一 礼敬と『釈門帰敬儀』
二 沙門不応拝俗表と道宣
三 拝不拝朝議の行方
四 不応拝俗論をめぐる彦〓と道宣
第十一章 道宣の絶筆三種
一 入寂
二 『律相感通伝』
三 『関中創立戒壇図経』
四 浄業寺戒壇
五 『中天竺舍衛国祇〓寺図経』
六 絶筆余譚
第十二章 薬師寺東塔の〓銘と西明寺鍾銘
一 薬師寺東塔
二 東塔〓銘
三 西明寺鍾銘
四 鍾銘と『広弘明集』
五 鍾銘より〓銘へ
六 鍾銘請来
附 篇
附篇第一章 北斉系官僚の一動向
一 隋文帝の誕生説話
二 『開皇起居注』
三 王劭とその周辺
四 周隋革命
五 著作郎王劭の革命説
六 隋朝と仏教
附篇第二章 王劭の著述小考
一 王劭略伝
二 『斉書』述仏志
三 述仏志と釈老志
四 『隋書』と王劭
五 『舎利感応記』
附篇第三章 末法家としての那連提黎耶舍——周隋革命と徳護長者経——
はじめに
一 那連提黎耶舍伝
二 耶舍の訳経事業
三 『大集月蔵経』と『蓮華面経』
四 『徳護長者経』
むすび
附篇第四章 中国の典籍に表われた祇〓精舍
はじめに
一 『金剛経』六訳と祇〓精舍
二 安世高の舍衛国・祇樹給孤独園
三 支婁迦讖・安玄・竺法護の祇〓精舍
四 法顕と祇〓精舍物語
五 中国の祇〓精舍縁起
六 『大唐西域記』と『中天竺舍衛国祇〓寺図経』
初出書誌一覧
索 引
要旨(中文、英文)