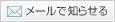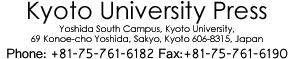Home > Book Detail Page
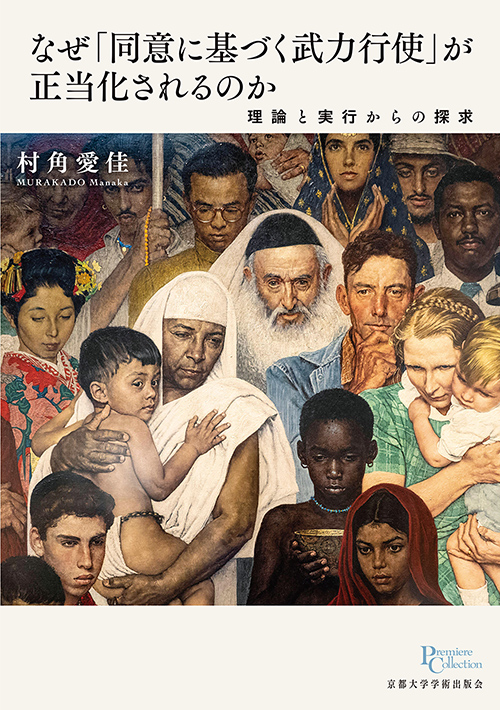
プリミエ・コレクション 138
なぜ「同意に基づく武力行使」が正当化されるのか
理論と実行からの探求
A5上製, 346 pages
ISBN: 9784814005642
pub. date: 02/25
ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルと周辺諸国との対立。いかなる逸脱も許されないはずの「武力行使の禁止」原則が、いま、いとも易々と破られている。領域国の同意があれば他国によるその領域での武力行使が許される、という論理はなぜまかり通ってしまうのか?「国家対国家」では零れ落ちるその理論的陥穽、国際法学の一大難問である「同意による正当化」に対し、「人間的視座」から新たな理論を提示。これまでの矛盾した議論を根本から塗り替える解法を、混迷の世界に提示する。
村角愛佳 (むらかど まなか)
神戸大学大学院法学研究科 特命助教。
金沢大学人間社会学域法学類 早期卒業。京都大学大学院法学研究科修士課程および博士後期課程 修了。日本学術振興会特別研究員(DC1)、京都大学大学院法学研究科 特定助教、ドイツ・マックスプランク比較公法・国際法研究所 客員研究員を経て、2024年より現職。
神戸大学大学院法学研究科 特命助教。
金沢大学人間社会学域法学類 早期卒業。京都大学大学院法学研究科修士課程および博士後期課程 修了。日本学術振興会特別研究員(DC1)、京都大学大学院法学研究科 特定助教、ドイツ・マックスプランク比較公法・国際法研究所 客員研究員を経て、2024年より現職。
序 章 国際法における国家・人間・武力行使
第1節 同意に基づく武力行使をめぐる問題と伝統的な国家対国家的視座の限界
I.同意に基づく武力行使をめぐる理論的・実践的問題
II.理論的問題に対する伝統的な国家対国家的視座からの先行研究
III.理論的問題における伝統的な国家対国家的視座の限界と、実践的問題との非関連性
第2節 武力行使禁止原則における人間的視座の必要性
I.国際法における人間的視座
II.国際法における人間的視座を武力行使禁止原則へ導入する必要性
第3節 本書の方法論、構成、用語の定義および射程
I.本書の方法論
I-1.国連憲章第2条4項と慣習法上の武力行使禁止原則の関係
I-2.武力行使の分野における国家実行の評価方法
II.本書の構成
III.用語の定義および射程
第1部 同意に基づく武力行使の理論
第1章 同意に基づく武力行使の既存の正当化理論
第1節 学説の議論状況の整理
I.違法性阻却説
II.武力行使禁止原則不適用説
第2節 両説の相違の根底にあるとされている対立
I.ILCにおける同意の法的位置付けをめぐる対立
II.ILCにおける対立と両説の相違の関連性
第2章 同意に基づく武力行使の正当化理論の再構築
第1節 同意の法的性質をめぐる対立の様相
I.同意内在説
II.同意内外区別説
第2節 同意に基づく武力行使の正当化理論における対立の真相
I.武力行使の文脈における議論の錯綜
II.武力行使禁止原則が強行規範であるという問題から回避する試み
III.武力行使禁止原則の国家対国家的視座とその限界
第3節 武力行使禁止原則の2元的理解による正当化理論の再構築
I.武力行使禁止原則の2元的理解の全体像
II.抽象的国家による抽象的国家利益の放棄としての武力行使への同意
III.武力行使禁止原則の2元的理解の基盤
IV.jus ad bellumに関する他の議論との関連
第2部 同意に基づく武力行使の実践
第3章 同意に基づく武力行使の実体的要件
第1節 学説の議論状況の整理
I.内戦不介入説
II.実効的支配説
III.民主的正統性説
IV.実効的保護説
第2節 実行の分析
I.内戦に至らない状況における同意に基づく武力行使
I-1.1998年の南アフリカ、ボツワナおよびジンバブエによるレソトでの武力行使
I-2.2006年のオーストラリアおよびニュージーランドによるトンガでの武力行使
I-3.2008年のAUによるコモロでの武力行使
I-4.2011年のGCCによるバーレーンでの武力行使
I-5.2014年のロシアによるウクライナでの武力行使
I-6.2017年のECOWASによるガンビアでの武力行使
I-7.2019年のフランスによるチャドでの武力行使
II.内戦における同意に基づく武力行使
II-1.1997年以降のナイジェリアおよびECOWASによるシエラレオネでの武力行使
II-2.2002年のフランスおよびECOWASによるコートジボワールでの武力行使
II-3.2013年のフランスによるマリでの武力行使
II-4.2014年の米国主導の連合軍、ロシアおよびイランによるイラクでの武力行使
II-5.2014年のウガンダによる南スーダンでの武力行使
II-6.2015年以降のロシアおよびイランによるシリアでの武力行使
II-7.2015年以降のサウジアラビア主導の連合軍によるイエメンでの武力行使
II-8.2020年以降のトルコによるリビアでの武力行使
第3節 実行に照らした諸説の評価
I.内戦不介入説の評価
II.実効的支配説の評価
III.民主的正統性説の評価
IV.実効的保護説の評価
第4節 武力行使禁止原則の2元的理解に基づく説明
I.実効的保護説の精緻化
II.武力行使国による一定の人間的利益の侵害の法的帰結
第4章 同意に基づく武力行使の手続的要件
第1節 同意を与える主体
I.同意が国家によって与えられること
II.同意が政府によって与えられること
III.同意が政府を代表する者によって与えられること
第2節 同意の態様
Ⅰ.同意が自由に与えられること
Ⅱ.同意が明確に確立されていること
第3節 同意を与える時期
I.同意が事前に与えられること
II.事前の条約による同意とアドホックな同意
II-1.理論的側面の分析
II-2.実行の分析
II-3.実行に照らした考察
III.アフリカにおける条約に基づく地域的安全保障システム
III-1.AUとECOWASにおける条約に基づく地域的安全保障システムの概要
III-2.理論的側面の分析
III-3.実行の分析
III-4.実行に照らした考察
第4節 武力行使禁止原則の2元的理解に基づく説明
I.駐留程度ではアドホックな同意は必要ないが、撤回は常時可能なのはいかに説明されるか
II.駐留を超える程度でもアドホックな同意が必要なく、かつ事前の同意が撤回不可能になる場合が認められれば、それはいかに説明されるか
第5章 自衛権の議論における同意に基づく武力行使の位置付け
第1節 集団的自衛権との関係
I.理論的側面の分析
II.実行の分析
II-1.1998年のジンバブエ、アンゴラおよびナミビアによるコンゴ民主共和国での武力行使
II-2.2011年のGCCによるバーレーンでの武力行使
II-3.2013年のフランスによるマリでの武力行使
II-4.2014年以降の米国主導の連合軍によるイラクおよびシリアでの武力行使
II-5.2015年以降のサウジアラビア主導の連合軍によるイエメンでの武力行使
II-6.2020年以降のトルコによるリビアでの武力行使
III.実行に照らした考察
IV.武力行使禁止原則の2元的理解に基づく説明
第2節 非国家主体の武力行為の国家への帰属をめぐる議論との関係
I.理論的側面の分析
II.実行の分析
II-1.1993年の米国によるイラクでの武力行使
II-2.1998年の米国によるスーダンおよびアフガニスタンでの武力行使
II-3.2001年の米国等によるアフガニスタンでの武力行使
II-4.2003年のイスラエルによるシリアでの武力行使
II-5.2006年のイスラエルによるレバノンでの武力行使
II-6.2008年のコロンビアによるエクアドルでの武力行使
III.実行に照らした考察
IV.武力行使禁止原則の2元的理解に基づく説明
第3節 非国家主体に対する自衛権をめぐる議論との関係
I.理論的側面の分析
I-1.非国家主体に対する自衛権をめぐる議論の分析
I-2.非国家主体に対する自衛権と同意に基づく武力行使の関係をめぐる議論の分析
II.実行の分析
II-1.2004年以降の米国によるパキスタンでの武力行使
II-2.2006年のエチオピアによるソマリアでの武力行使
II-3.2007年以降の米国によるソマリアでの武力行使
II-4.2011年のケニアによるソマリアでの武力行使
II-5.2014年以降の米国主導の連合軍、ロシアおよびイランによるイラクでの武力行使
II-6.2014年以降の米国主導の連合軍によるシリアでの武力行使
II-7.2015年のエジプトによるリビアでの武力行使
II-8.2015年以降の米国によるリビアでの武力行使
III.実行に照らした考察
IV.武力行使禁止原則の2元的理解に基づく説明
第4節 国家の同意と自衛権の関係性―第5章の検討結果を踏まえて
終 章 理論と実践の狭間で
第1節 結 論
第2節 今後の課題
I.jus ad bellumに関する他の諸論点の検討
II.武力行使禁止原則を含めた国際法一般における人間的視座の理論化
あとがき
主要参考文献一覧
I.日本語文献
II.外国語文献
索引
第1節 同意に基づく武力行使をめぐる問題と伝統的な国家対国家的視座の限界
I.同意に基づく武力行使をめぐる理論的・実践的問題
II.理論的問題に対する伝統的な国家対国家的視座からの先行研究
III.理論的問題における伝統的な国家対国家的視座の限界と、実践的問題との非関連性
第2節 武力行使禁止原則における人間的視座の必要性
I.国際法における人間的視座
II.国際法における人間的視座を武力行使禁止原則へ導入する必要性
第3節 本書の方法論、構成、用語の定義および射程
I.本書の方法論
I-1.国連憲章第2条4項と慣習法上の武力行使禁止原則の関係
I-2.武力行使の分野における国家実行の評価方法
II.本書の構成
III.用語の定義および射程
第1部 同意に基づく武力行使の理論
第1章 同意に基づく武力行使の既存の正当化理論
第1節 学説の議論状況の整理
I.違法性阻却説
II.武力行使禁止原則不適用説
第2節 両説の相違の根底にあるとされている対立
I.ILCにおける同意の法的位置付けをめぐる対立
II.ILCにおける対立と両説の相違の関連性
第2章 同意に基づく武力行使の正当化理論の再構築
第1節 同意の法的性質をめぐる対立の様相
I.同意内在説
II.同意内外区別説
第2節 同意に基づく武力行使の正当化理論における対立の真相
I.武力行使の文脈における議論の錯綜
II.武力行使禁止原則が強行規範であるという問題から回避する試み
III.武力行使禁止原則の国家対国家的視座とその限界
第3節 武力行使禁止原則の2元的理解による正当化理論の再構築
I.武力行使禁止原則の2元的理解の全体像
II.抽象的国家による抽象的国家利益の放棄としての武力行使への同意
III.武力行使禁止原則の2元的理解の基盤
IV.jus ad bellumに関する他の議論との関連
第2部 同意に基づく武力行使の実践
第3章 同意に基づく武力行使の実体的要件
第1節 学説の議論状況の整理
I.内戦不介入説
II.実効的支配説
III.民主的正統性説
IV.実効的保護説
第2節 実行の分析
I.内戦に至らない状況における同意に基づく武力行使
I-1.1998年の南アフリカ、ボツワナおよびジンバブエによるレソトでの武力行使
I-2.2006年のオーストラリアおよびニュージーランドによるトンガでの武力行使
I-3.2008年のAUによるコモロでの武力行使
I-4.2011年のGCCによるバーレーンでの武力行使
I-5.2014年のロシアによるウクライナでの武力行使
I-6.2017年のECOWASによるガンビアでの武力行使
I-7.2019年のフランスによるチャドでの武力行使
II.内戦における同意に基づく武力行使
II-1.1997年以降のナイジェリアおよびECOWASによるシエラレオネでの武力行使
II-2.2002年のフランスおよびECOWASによるコートジボワールでの武力行使
II-3.2013年のフランスによるマリでの武力行使
II-4.2014年の米国主導の連合軍、ロシアおよびイランによるイラクでの武力行使
II-5.2014年のウガンダによる南スーダンでの武力行使
II-6.2015年以降のロシアおよびイランによるシリアでの武力行使
II-7.2015年以降のサウジアラビア主導の連合軍によるイエメンでの武力行使
II-8.2020年以降のトルコによるリビアでの武力行使
第3節 実行に照らした諸説の評価
I.内戦不介入説の評価
II.実効的支配説の評価
III.民主的正統性説の評価
IV.実効的保護説の評価
第4節 武力行使禁止原則の2元的理解に基づく説明
I.実効的保護説の精緻化
II.武力行使国による一定の人間的利益の侵害の法的帰結
第4章 同意に基づく武力行使の手続的要件
第1節 同意を与える主体
I.同意が国家によって与えられること
II.同意が政府によって与えられること
III.同意が政府を代表する者によって与えられること
第2節 同意の態様
Ⅰ.同意が自由に与えられること
Ⅱ.同意が明確に確立されていること
第3節 同意を与える時期
I.同意が事前に与えられること
II.事前の条約による同意とアドホックな同意
II-1.理論的側面の分析
II-2.実行の分析
II-3.実行に照らした考察
III.アフリカにおける条約に基づく地域的安全保障システム
III-1.AUとECOWASにおける条約に基づく地域的安全保障システムの概要
III-2.理論的側面の分析
III-3.実行の分析
III-4.実行に照らした考察
第4節 武力行使禁止原則の2元的理解に基づく説明
I.駐留程度ではアドホックな同意は必要ないが、撤回は常時可能なのはいかに説明されるか
II.駐留を超える程度でもアドホックな同意が必要なく、かつ事前の同意が撤回不可能になる場合が認められれば、それはいかに説明されるか
第5章 自衛権の議論における同意に基づく武力行使の位置付け
第1節 集団的自衛権との関係
I.理論的側面の分析
II.実行の分析
II-1.1998年のジンバブエ、アンゴラおよびナミビアによるコンゴ民主共和国での武力行使
II-2.2011年のGCCによるバーレーンでの武力行使
II-3.2013年のフランスによるマリでの武力行使
II-4.2014年以降の米国主導の連合軍によるイラクおよびシリアでの武力行使
II-5.2015年以降のサウジアラビア主導の連合軍によるイエメンでの武力行使
II-6.2020年以降のトルコによるリビアでの武力行使
III.実行に照らした考察
IV.武力行使禁止原則の2元的理解に基づく説明
第2節 非国家主体の武力行為の国家への帰属をめぐる議論との関係
I.理論的側面の分析
II.実行の分析
II-1.1993年の米国によるイラクでの武力行使
II-2.1998年の米国によるスーダンおよびアフガニスタンでの武力行使
II-3.2001年の米国等によるアフガニスタンでの武力行使
II-4.2003年のイスラエルによるシリアでの武力行使
II-5.2006年のイスラエルによるレバノンでの武力行使
II-6.2008年のコロンビアによるエクアドルでの武力行使
III.実行に照らした考察
IV.武力行使禁止原則の2元的理解に基づく説明
第3節 非国家主体に対する自衛権をめぐる議論との関係
I.理論的側面の分析
I-1.非国家主体に対する自衛権をめぐる議論の分析
I-2.非国家主体に対する自衛権と同意に基づく武力行使の関係をめぐる議論の分析
II.実行の分析
II-1.2004年以降の米国によるパキスタンでの武力行使
II-2.2006年のエチオピアによるソマリアでの武力行使
II-3.2007年以降の米国によるソマリアでの武力行使
II-4.2011年のケニアによるソマリアでの武力行使
II-5.2014年以降の米国主導の連合軍、ロシアおよびイランによるイラクでの武力行使
II-6.2014年以降の米国主導の連合軍によるシリアでの武力行使
II-7.2015年のエジプトによるリビアでの武力行使
II-8.2015年以降の米国によるリビアでの武力行使
III.実行に照らした考察
IV.武力行使禁止原則の2元的理解に基づく説明
第4節 国家の同意と自衛権の関係性―第5章の検討結果を踏まえて
終 章 理論と実践の狭間で
第1節 結 論
第2節 今後の課題
I.jus ad bellumに関する他の諸論点の検討
II.武力行使禁止原則を含めた国際法一般における人間的視座の理論化
あとがき
主要参考文献一覧
I.日本語文献
II.外国語文献
索引