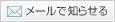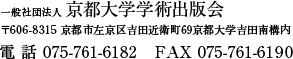ホーム > 書籍詳細ページ
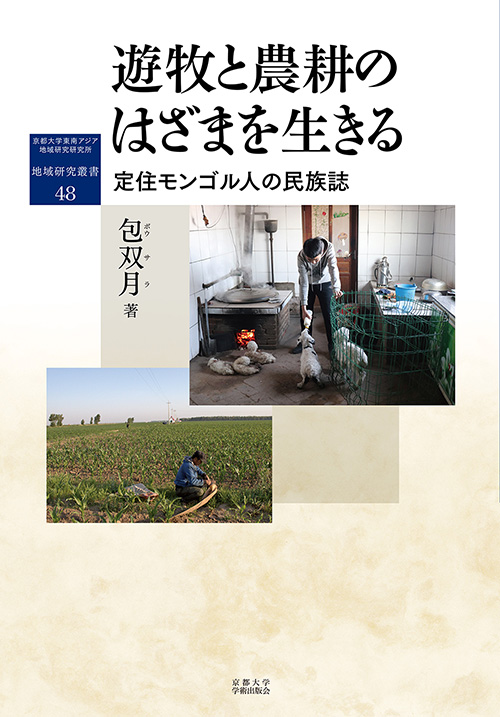
近代化以降、中国内モンゴル自治区東部地域のモンゴル人は定住・農耕化し、半農半牧の生活を創出してきた。過酷な自然環境、複数の近代国家にまたがる激動に常に揺さぶられつつ、生活実践と生業構成、土地所有意識や伝統の概念をダイナミックに変貌させる彼らは、自らを「はざま」に生きる人びとと称する。独立国・牧畜・移動・放牧技術に偏っていた従来の人類学的モンゴル研究を乗り越え、「遊牧」という概念自体の理解をも捉え直す民族誌。
包 双月(ボウ サラ)
内モンゴル自治区生まれ。2021年9月、東北大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。日本学術研究員特別研究員DC2を経て、東北大学大学院文学研究科助教。
主な業績として、「出稼ぎに行くのは甲斐性のない人―モンゴル人の移動と生活基盤」川口幸大・堀江未央編『中国の国内移動―内なる他者との邂逅』京都大学学術出版会(2020年)、「定住農耕モンゴル人の編み出す民俗知―屠畜の多様化と肉食行為の変化をめぐって」『文化人類学』88巻1号(2023年)、「ネイティヴ人類学者になるということ―日本で人類学を学んだモンゴル人人類学者の事例から」沼崎一郎監修、西川慧、リーペレス・ファビオ、中野惟文、包双月編『多軸的な自己を生きる―交差するポジショナリティのオートエスノグラフィ』東北大学出版会(2024年)ほか。
内モンゴル自治区生まれ。2021年9月、東北大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。日本学術研究員特別研究員DC2を経て、東北大学大学院文学研究科助教。
主な業績として、「出稼ぎに行くのは甲斐性のない人―モンゴル人の移動と生活基盤」川口幸大・堀江未央編『中国の国内移動―内なる他者との邂逅』京都大学学術出版会(2020年)、「定住農耕モンゴル人の編み出す民俗知―屠畜の多様化と肉食行為の変化をめぐって」『文化人類学』88巻1号(2023年)、「ネイティヴ人類学者になるということ―日本で人類学を学んだモンゴル人人類学者の事例から」沼崎一郎監修、西川慧、リーペレス・ファビオ、中野惟文、包双月編『多軸的な自己を生きる―交差するポジショナリティのオートエスノグラフィ』東北大学出版会(2024年)ほか。
凡 例
はじめに
序章 「らしくない」モンゴル人の民族誌
第1節 問題の所在
第2節 先行研究
1 遊牧/牧畜の研究史
2 モンゴルの表象
第3節 周辺の人類学者として
第4節 本書の視座
1 定住中心主義と遊牧民
2 人間中心主義からの脱却
3 新たな視座を求めて
4 調査地およびフィールドワーク
第5節 本書の構成
第Ⅰ部 モンゴル世界における遊牧と定住のダイナミクス
第1章 作物を育てる遊牧民—牧畜システムと遊牧との連続性
第1節 モンゴルの牧畜システムの特徴
1 高い移動性
2 家畜の活用のあり方
3 去勢オス畜の利用
第2節 家畜利用の実態
1 食体系
2 畜産品の利用
第3節 拡張的発展
1 遊牧社会と農業社会の相違
2 社会環境からみる遊牧民
第4節 自然農法
1 モンゴル高原における農業
2 ナムク・タリヤ農法
3 モンゴル・アム(モンゴルの穀物)
第5節 遊牧を定住から再考する
コラム1 乳加工品
第2章 周辺の「周辺」—内モンゴル自治区東部地域の特色
第1節 内モンゴル自治区
1 内モンゴルの自然環境
2 内モンゴルの社会環境
第2節 モンゴル世界の一部としての東部地域
1 東部地域という空間認識の形成
2 モンゴル社会の一端としての東部地域
第3節 中華世界の周辺としての東部地域
第4節 定住農耕モンゴル人の村落
1 通遼市の特徴
2 調査村落の概要
コラム2 モンゴルにおける仏教
第Ⅱ部 定住農耕モンゴル人の民族誌を記述する
第3章 農業の導入—牧畜生活との関係と二重の意義
第1節 栽培作物と耕作の実態
第2節 ナムク・タリヤの展開
第3節 シャンタイ・タリヤの開始
1 バヤン・アイル
2 ウニル・アイル
第4節 農業がもつ二重の意義
第4章 ブタの飼育と利用の開始—食肉行為の変化と新たな民俗知
第1節 動物との多様なかかわり方
1 遊牧民の家畜と農耕民の家畜
2 矛盾を孕む家畜、ブタ
第2節 ブタ導入の必要性および飼育方法
1 ブタ導入の必要性
2 モンゴル人のブタの飼育方法
3 漢人のブタの飼育方法
4 モンゴル人と漢人のブタ飼育の比較分析
第3節 屠畜からみるブタ利用
1 「伝統」家畜の解体方法
2 ブタの解体方法
3 「伝統」家畜とブタの解体方法の比較分析
第4節 民俗分類体系からみるブタ利用
1 モンゴル人と漢人におけるブタ肉の民俗分類
2 ブタ肉の利用実態
3 内臓の利用実態
4 肉を主食とする
第5節 定住農耕モンゴル人にとってのブタ
第5章 牧畜の変容—農耕化と市場経済化の二重の影響
第1節 家畜飼育形態の変化
1 バヤン・アイルの牧畜経営
2 ウニル・アイルの牧畜経営
3 フデ・アイルの牧畜経営
4 共通点と相違点
第2節 家畜用飼料の変化
第3節 家畜の出産管理の変容
1 ウシの出産管理
2 ヒツジの出産管理
第4節 家畜利用形態の変容
1 メス維持型牧畜へ
2 搾乳しない牧畜経営
第5節 家畜の習性に合わせた生き方の持続と変容
第6章 土地利用形態とその変化—土地賃貸システムと「資源化」意識の誕生
第1節 土地制度の歴史
1 清朝によるモンゴル統治
2 藩部としてのモンゴル地域
3 蒙地開墾
第2節 土地制度の近代化
1 満洲国の土地政策
2 中華人民共和国の土地政策
第3節 土地使用権の分配プロセス
1 バヤン・アイル
2 ウニル・アイル
3 フデ・アイル
第4節 土地のもつ意味の変化
第7章 社会変容の諸相—社会構造、年中行事、通過儀礼、ホルチン民謡
第1節 社会構造の変容
1 ノトグの多義性
2 アイル(世帯)から「アイル」(村落)へ
3 強化される地縁関係
第2節 通過儀礼の変容
1 出産儀礼
2 婚姻儀礼
3 ジル・オロホ
4 葬式
5 儀礼の語りの変容と追加される儀礼
第3節 年中行事の変容
第4節 民謡と民俗楽器の資源化
1 ホルチン民謡
2 民俗楽器
第5節 遊牧から定住農耕化へ
終章 はざまを生きる
第1節 遊牧と農業のはざまで
第2節 移動と定住のはざまで
第3節 モンゴルと中華のはざまで
第4節 「遊牧論」の再考と展望
引用文献
あとがき
索 引
はじめに
序章 「らしくない」モンゴル人の民族誌
第1節 問題の所在
第2節 先行研究
1 遊牧/牧畜の研究史
2 モンゴルの表象
第3節 周辺の人類学者として
第4節 本書の視座
1 定住中心主義と遊牧民
2 人間中心主義からの脱却
3 新たな視座を求めて
4 調査地およびフィールドワーク
第5節 本書の構成
第Ⅰ部 モンゴル世界における遊牧と定住のダイナミクス
第1章 作物を育てる遊牧民—牧畜システムと遊牧との連続性
第1節 モンゴルの牧畜システムの特徴
1 高い移動性
2 家畜の活用のあり方
3 去勢オス畜の利用
第2節 家畜利用の実態
1 食体系
2 畜産品の利用
第3節 拡張的発展
1 遊牧社会と農業社会の相違
2 社会環境からみる遊牧民
第4節 自然農法
1 モンゴル高原における農業
2 ナムク・タリヤ農法
3 モンゴル・アム(モンゴルの穀物)
第5節 遊牧を定住から再考する
コラム1 乳加工品
第2章 周辺の「周辺」—内モンゴル自治区東部地域の特色
第1節 内モンゴル自治区
1 内モンゴルの自然環境
2 内モンゴルの社会環境
第2節 モンゴル世界の一部としての東部地域
1 東部地域という空間認識の形成
2 モンゴル社会の一端としての東部地域
第3節 中華世界の周辺としての東部地域
第4節 定住農耕モンゴル人の村落
1 通遼市の特徴
2 調査村落の概要
コラム2 モンゴルにおける仏教
第Ⅱ部 定住農耕モンゴル人の民族誌を記述する
第3章 農業の導入—牧畜生活との関係と二重の意義
第1節 栽培作物と耕作の実態
第2節 ナムク・タリヤの展開
第3節 シャンタイ・タリヤの開始
1 バヤン・アイル
2 ウニル・アイル
第4節 農業がもつ二重の意義
第4章 ブタの飼育と利用の開始—食肉行為の変化と新たな民俗知
第1節 動物との多様なかかわり方
1 遊牧民の家畜と農耕民の家畜
2 矛盾を孕む家畜、ブタ
第2節 ブタ導入の必要性および飼育方法
1 ブタ導入の必要性
2 モンゴル人のブタの飼育方法
3 漢人のブタの飼育方法
4 モンゴル人と漢人のブタ飼育の比較分析
第3節 屠畜からみるブタ利用
1 「伝統」家畜の解体方法
2 ブタの解体方法
3 「伝統」家畜とブタの解体方法の比較分析
第4節 民俗分類体系からみるブタ利用
1 モンゴル人と漢人におけるブタ肉の民俗分類
2 ブタ肉の利用実態
3 内臓の利用実態
4 肉を主食とする
第5節 定住農耕モンゴル人にとってのブタ
第5章 牧畜の変容—農耕化と市場経済化の二重の影響
第1節 家畜飼育形態の変化
1 バヤン・アイルの牧畜経営
2 ウニル・アイルの牧畜経営
3 フデ・アイルの牧畜経営
4 共通点と相違点
第2節 家畜用飼料の変化
第3節 家畜の出産管理の変容
1 ウシの出産管理
2 ヒツジの出産管理
第4節 家畜利用形態の変容
1 メス維持型牧畜へ
2 搾乳しない牧畜経営
第5節 家畜の習性に合わせた生き方の持続と変容
第6章 土地利用形態とその変化—土地賃貸システムと「資源化」意識の誕生
第1節 土地制度の歴史
1 清朝によるモンゴル統治
2 藩部としてのモンゴル地域
3 蒙地開墾
第2節 土地制度の近代化
1 満洲国の土地政策
2 中華人民共和国の土地政策
第3節 土地使用権の分配プロセス
1 バヤン・アイル
2 ウニル・アイル
3 フデ・アイル
第4節 土地のもつ意味の変化
第7章 社会変容の諸相—社会構造、年中行事、通過儀礼、ホルチン民謡
第1節 社会構造の変容
1 ノトグの多義性
2 アイル(世帯)から「アイル」(村落)へ
3 強化される地縁関係
第2節 通過儀礼の変容
1 出産儀礼
2 婚姻儀礼
3 ジル・オロホ
4 葬式
5 儀礼の語りの変容と追加される儀礼
第3節 年中行事の変容
第4節 民謡と民俗楽器の資源化
1 ホルチン民謡
2 民俗楽器
第5節 遊牧から定住農耕化へ
終章 はざまを生きる
第1節 遊牧と農業のはざまで
第2節 移動と定住のはざまで
第3節 モンゴルと中華のはざまで
第4節 「遊牧論」の再考と展望
引用文献
あとがき
索 引